
冬でも暖かい便座に座り、 ボタン一つで、人肌のお湯が、優しくおしりを洗い流してくれる。
その、あまりに快適で、清潔な時間。 今や、日本の家庭や公共施設のトイレでは、当たり前の光景です。
しかし、もしその当たり前が、かつて「お尻を水で洗うなんて、とんでもない!」という、日本社会全体の巨大な「心の壁]に、たった一社が、社運を賭けて挑んだ、壮絶な戦いの末に勝ち取られたものだとしたら。
これは、単なる便利な製品の開発物語ではありません。 「日本のトイレを、世界一快適な場所にしたい」という、一つの企業の燃えるような「思い」が、いかにして人々の固定観念を覆し、新しい文化を創造したのか。その軌跡を追う、革命の物語です。
この記事を読み終える頃、あなたがトイレのボタンを押すその指先に、日本の「おもててなし」の神髄と、技術者たちの、少しおかしくも、真摯な執念の記憶が宿るはずです。
すべての始まり:海の向こうの「医療器具」と、一つの野望
物語は、1960年代。 その原型となる製品は、実はアメリカで生まれていました。しかし、それは痔の治療などに使われる、高価な「医療器具」であり、一般家庭に普及するようなものではありませんでした。
この、海の向こうの珍しい製品に、大きな可能性を見出したのが、日本の衛生陶器メーカー「TOTO」でした。 当時の日本のトイレは、まだ和式が主流。暗く、臭く、冬は冷たい。そんなイメージが一般的でした。
「日本のトイレを、もっと明るく、清潔で、快適な場所にできないだろうか?」 「この医療器具を、誰もが使える快適な製品として、日本の家庭に届けられないか?」
それは、単に新しい製品を売りたい、というビジネス的な発想を超えた、日本の生活文化そのものを、より豊かにしたいという、壮大な野望でした。
高すぎる壁:日本人の「心」という、最難関
しかし、その野望の前には、これまでとは比較にならないほど、巨大で、分厚い壁が立ちはだかっていました。
- 壁①「羞恥心」という、見えない怪物 「お尻を、水で洗う」。 その行為自体が、当時の日本人にとっては、未知であり、口にするのもはばかられるような、強い羞恥心を伴うものでした。製品の良さを伝える以前に、そもそも話題にすること自体が、タブー視されていたのです。
- 壁②「神の領域」への挑戦 もし使ってもらえたとしても、そこは人間の体で、最もデケートな部分。お湯の「温度」は、何度が一番心地よいのか?お湯を当てる「角度」は?そして、「水流の強さ」は? 熱すぎても、冷たすぎてもいけない。角度がズレれば、不快極まりない。強すぎても、弱すぎてもダメ。その「黄金のバランス」を見つけ出すことは、まさに神の領域に挑むような、前代未聞の挑戦でした。
- 壁③「水と電気」の悪夢、再び そして、水回りで使う家電が必ず直面する、あの宿命的な壁。常に水が存在するトイレという空間で、電気を使う製品の安全性を、どうやって完璧に担保するのか。感電や漏電のリスクは、絶対に許されませんでした。
執念の突破口:「黄金の角度」と、テレビCMという賭け
TOTOの技術者たちは、この三つの壁に、驚くべき執念と、前代未聞の作戦で挑みます。
まず、最大の壁であった「神の領域」。 彼らは、「最適なお湯の位置を見つけるため、社員に協力を求めた」のです。開発チームは、中央に一本の糸を垂らしただけの、秘密の「測定椅子」を用意。社内のあらゆる部署にお願いして回り、実に300人もの社員に座ってもらい、日本人のお尻の「平均位置」という、それまで誰も知らなかった貴重なデータを、手作業で集めていきました。さらに、開発室の実験用便座で、来る日も来る日も自ら「快適さ」を検証し、ついに「43度のお湯」が「43度の角度」で当たるのが、最も快適であるという「黄金のバランス」を突き止めたのです。
そして、最大の賭けであった「羞恥心」という壁。 1982年、TOTOは、社運を賭けた、一つのテレビCMを放映します。しかし、その道のりは平坦ではありませんでした。「食事の時間帯に、トイレのCMなど非常識だ」と、社内からは猛烈な反対の声が上がります。役員会議は何度も紛糾しましたが、最終的には「本当に良いものであれば、必ず受け入れられる」という、当時の社長の鶴の一声で、この大博打は決行されました。
日本を代表するコピーライター・仲畑貴志氏が生み出した、あの伝説の一言。 そして、サブカルチャーのアイコンであった女優・戸川純さんが、少し困ったような、それでいてチャーミングな表情で、こう問いかけるのです。
「おしりだって、洗ってほしい。」
それは、日本中のお茶の間に、衝撃と、少しの笑いを届けました。今まで誰もが口に出せなかったことを、明るく、お洒落に言い放ったこの一言は、見事に日本人の「心の壁」を打ち破り、「ウォシュレット」という名前を、一躍国民的なものにしたのです。
結論:ボタン一つは、日本の「おもてなし」
「ウォシュレット」の登場は、日本のトイレを、単なる排泄の場所から、「世界一快適な空間」へと進化させました。
そのボタン一つ一つには、 「日本のトイレ文化を変えたい」と願った、企業の野望。 そして、社員300人のお尻のデータと、数えきれない試行錯誤の末に「黄金の角度」を見つけ出した、技術者たちの、少しおかしくも、真摯な執念が込められているのです。
それは、日本が世界に誇る「おもてなし」の心の、最も象徴的な形なのかもしれません。

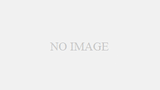
コメント