[モダンなビデオインターホンと、玄関のドアの画像]

「ピンポーン」という、軽快なチャイムの音。 私たちは、リビングの壁にあるモニターに目をやり、 そこに映る訪問者の顔を確認してから、ドアを開ける。
声だけでなく、 顔が見えるという、絶対的な安心感。
私たちは、その安全を、当たり前の日常として生きています。
しかし、もしその「顔が見える」という当たり前が、かつて、見知らぬ訪問者への「恐怖」から、家族を守りたいと願った、日本の技術者たちの執念の末に生まれたとしたら。
これは、単なる便利な製品の開発物語ではありません。 戦後の日本社会が抱えた「不安」という壁に、技術者たちの「思い」が、いかにして「目」という名の突破口をこじ開けたのか。その軌跡を追う、防犯革命の物語です。
この記事を読み終える頃、あなたがインターホンの応答ボタンを押すその指先に、家族の安全を願った、先人たちの温かい眼差しを感じるはずです。
すべての始まり:ドア越しの「声」と、消えない不安
物語は、まだインターホンにカメラがなかった時代から始まります。 もちろん、玄関の呼び鈴に応答し、声だけで会話をする「ドアホン」は存在しました。
しかし、そこには、拭いきれない一つの「不安」がありました。 「この声は、本当に、名乗っている通りの人物なのだろうか?」
特に、戦後の高度経済成長期、都市部にはアパートや団地といった集合住宅が急増します。隣に誰が住んでいるのかも分からない。そんな新しい住環境の中で、悪質な訪問販売や、時には見知らぬ人物を装った犯罪への不安が、静かに、しかし確実に、社会全体に広がっていきました。
声だけでは、安心できない。 ドアを開ける前、最後の瞬間に、相手の「顔」を確認したい。
それは、単なる利便性の追求ではありませんでした。 見知らぬ訪問者という「恐怖」から、家にいる大切な家族を守りたいという、切切な願い。それが、すべての始まりでした。
高すぎる壁:玄関に「目」を持つことの、三つの困難
「ドアの向こうを、映像で見たい」。 そのシンプルな夢を実現するためには、当時の技術では、あまりに高い壁が立ちはだかっていました。
- 壁①「巨大な目玉」という、物理的な壁 映像を映し出すには、ブラウン管のモニターが必要です。しかし、当時のブラウン管は、奥行きが長く、大きく、そして高価なものでした。これを、家庭の壁に埋め込めるほど小さく、薄くすることは、不可能に近い挑戦でした。
- 壁②「暗闇」という、自然の壁 訪問者は、いつも明るい昼間に来てくれるとは限りません。夜間や、日陰になった玄関先でも、相手の顔をはっきりと認識できなければ、防犯の「目」としての意味がありません。わずかな光でも鮮明な映像を捉える、高感度なカメラ技術が必要でした。
- 壁③「そこまでする必要ある?」という、心の壁 そして、最大の壁は、人々の心の中にありました。「ご近所付き合い」がまだ当たり前だった時代に、玄関先にカメラを設置することは、「隣人を疑っているのか」という、過剰防衛のような印象を与えかねませんでした。「うちには、そんな大げさなものは必要ない」という、心理的な抵抗感も、大きな壁でした。
執念の突破口:団地から始まった、日本の「安心」革命
この三つの壁に、果敢に挑んだのが、アイホン株式会社をはじめとする、日本の技術者たちでした。
まず、最大の壁であった「巨大な目玉」。 ブラウン管は、奥にある電子銃から電子ビームを飛ばして絵を映す仕組み上、薄くするのが極めて困難でした。技術者たちは、電子ビームを大きく曲げるための偏向ヨークという部品の設計に、来る日も来る日も取り組みます。しかし、無理に曲げれば映像は歪む。まさに、1ミリ単位で無駄を削ぎ落とし、歪みを補正する、地道で、気の遠くなるような作業でした。そしてついに、家庭の壁にも収まる、世界最小クラスのモニターを開発することに成功します。
次に、「暗闇」という壁。 ただ照明をつけるだけでは、訪問者を眩惑させてしまい、かえって顔が見えません。そこで彼らが編み出したのが、「赤外線LED」という、目に見えない光の活用でした。訪問者がボタンを押した瞬間だけ、強力な赤外線LEDが顔を照らし出す。人間の目にはただの暗闇でも、カメラの目には、相手の顔がくっきりと映し出される。この、相手に不快感を与えない、スマートな解決策にたどり着くまで、彼らは幾度となく夜の実験を繰り返したのです。
そして、最後の壁「人々の心」。 この壁を打ち破ったのは、皮肉にも、社会に広がり始めた「不安」でした。セールスマンを装った犯罪などがメディアで報じられるようになると、人々の防犯意識は急速に高まります。技術者たちは、この時代の空気の変化を敏感に察知しました。彼らは、特に新しい住環境に不安を感じていた都市部の団地やマンションの建設業者に狙いを定め、「この一台が、奥さんとお子さんを、危険から守ります」と、その価値を粘り強く説いて回ったのです。
やがて、テレビ付きインターホンは「特別な防犯設備」ではなく、「新しいマンションの標準装備」として、ごく自然に日本の家庭に溶け込んでいきました。
結論:ボタン一つは、家族を守る「眼差し」
インターホンのモニターに、訪問者の顔が映し出される。 その当たり前の光景は、
「家族を、不安から守りたい」と願った、企業の思い。 そして、巨大なブラウン管と格闘し、暗闇の中でも顔が見えるカメラを開発した、技術者たちの執念。
その両者が生み出した、日本が世界に誇る「安心」の文化なのです。

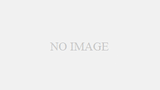
コメント