はじめに
このブログは、20代の私が、悩み、試行錯誤しながら経験してきた「やっておいて良かったこと」や「知っておけば良かったこと」から得られた“気づき”を、未来に生まれてくる自分の子供に向けて書き残す、個人的なブログです。
そして、もしこの記事が未来の自分の子供だけでなく、今を生きるあなたの人生にとっても、ほんの少しでもプラスになったら嬉しいです!
Step 1: 私たちの「当たり前」は、本当に当たり前なのだろうか?
深夜でも、女性が一人でコンビニエンスストアに行ける国、日本。
私たちは、この世界最高水準の「安全」という環境で、当たり前のように暮らしています。
でも、もし、その「当たり前」が、一歩海外に出た途端、蜃気楼のように消え去ってしまうとしたら?
私がフィリピンのセブ島で過ごした1ヶ月は、まさにそんな、自分の「常識」がガラガラと音を立てて壊されていく日々の連続でした。
そしてその経験は、私の人生の見え方を大きく変えることになりました。
Step 2: 銃、ストリートチルドレン、そして「エリート」の先生
セブ島といえば、有名なリゾート地。 大学生の定番な海外旅行先の一つでもあり、新婚旅行先にも選ばれることも多い。
そんなリゾート地だと思っていたのですが、現実は私の理想とかけ離れていました。
セブンイレブンの入り口には、ショットガンを抱えた警備員。
寮から学校まで、たった1分の距離なのに、毎日送迎してくれるスクールバス。
街を歩いていると、物乞いのために寄ってくるストリートチルドレンたち。
そして、学校で出会った光景も、私に強い衝撃を与えました。
フィリピンではエリート職の一つである英語の先生が、鼻をかんだティッシュでそのまま目を拭いたり、「薬は信用ならない」と言ってフルーツジュースを飲んだりする。
食事は肉ばかりで、野菜をほとんど摂らない。
- なぜ、日本とこれほどまでに違うのか?
- なぜ、これほどの知識を持つはずの「先生」でさえ、私たちが当たり前だと考える衛生観念や健康知識を持っていないことがあるのか?
この、身の安全から教育レベルまで、色々な面での「違い」の根源を知りたくて、私はその背景を調べてみました。
Step 3: なぜ?を解き明かすための「3つの考察」
なぜ、日本とフィリピンの「当たり前」は、これほどまでに違うのか?
その答えは、個人の努力や国民性の問題では決してありませんでした。
それは、両国が歩んできた「歴史」「地政学的な立場」そして「教育システムの構造」という、もっと大きな構造の中に隠されていたのです。
この複雑な「なぜ?」を、3つの観点から考察してみました。
考察①:400年続いた「植民地支配の歴史」
日本が明治維新以降、独立を保ちながら近代化を進めた一方、フィリピンは、スペインとアメリカによる約400年もの長い植民地支配を経験しました。
特に、スペインは一部の地主やエリート層のみに高等教育を施し、大多数の国民を教育から遠ざけました。
アメリカは公教育制度を導入したものの、それはあくまでアメリカの統治に都合の良い、英語を話す労働力を育成するためのものでした。
この歴史は、一部の富裕層が国の富と権力を独占し、その他大多数の国民が貧困から抜け出しにくいという社会構造を、根深く形成してしまいました。
国の「スタートライン」が、そもそも全く違ったのです。
考察②:第二次大戦後の「異なる発展の道」
第二次大戦後、日本が「ものづくり」を軸とした官民一体の国家戦略で「高度経済成長」という奇跡的な復興を遂げた時代、フィリピンは長期の独裁政権下で、国の富が不正に海外へ流用され、国全体の発展が大きく阻害されるという、異なる道を歩みました。
本来であれば、道路や学校、病院といった社会基盤の整備に向けられるはずだった巨額の資金が失われ、多くの国民が豊かになる機会、そして質の高い教育を受ける機会が、歴史のある時点で奪われてしまったのです。
考察③:「教育の質と機会」の構造的な格差
フィリピンの識字率は約96%と高い一方、10歳児の9割が簡単な文章を理解できない「学習の貧困」が深刻な問題となっています。
これは、文字を「読める」ことと、内容を「理解して活用できる」ことの間に、大きな溝があることを示しています。
その背景には、教室や教材の圧倒的な不足、そして教員の低賃金といった「教育資源の不足」があります。
公立学校では1クラス50人以上いることもあり、教科書は数人で1冊を共有することも珍しくありません。
このような環境では、一人ひとりに合わせた質の高い教育を提供することは極めて困難です。
私が会った先生の行動も、個人的な資質というより、こうした「質の高い健康教育や科学的知識に触れる機会」そのものが、社会全体に行き渡っていないことの、一つの悲しい表れだったのかもしれません。
これらの考察を通して、目の前の光景が、単なる感情論ではなく、その背景にあるシステムとして、パッと色づいて見えるような感覚でした。
Step 4: 「なぜ?」と「答え」が繋がる瞬間
この新しい視点を手にした時、私はもう一度、セブ島の光景を心の中で思い返してみました。 すると、かつて私が抱いた「なぜ?」の答えが、驚くほどクリアに見えてきたのです。
なぜ、ストリートチルドレンがいるのか?
その答えは、考察①と②で見たように、一部の富裕層に富が集中する社会構造が固定化され、多くの人々が貧困から抜け出す術を持たない、という現実にありました。 子供が学校へ行くよりも、その日の食事のために路上で働くことを選ばざるを得ない。
それは、彼らにとって、極めて合理的な選択なのです。
なぜ、コンビニの前に銃を持った警備員がいるのか?
その答えもまた、この極端な富の偏在にあります。それが社会に深刻な緊張感を生み出しているからです。
銃は、その歪んだ社会構造を、物理的に維持するための、悲しい象徴に他なりません。
なぜ、エリートであるはずの先生が、非科学的な行動をとることがあるのか?
その理由も、考察③で触れた、国全体の教育システムが十分な資源と質を担保できていない、という点に繋がります。
「学習の貧困」は、子供だけでなく、大人、そして社会全体に静かに浸透しているのです。
そして同時に、私たちが生きる日本の「安全」や「豊かさ」、そして「当たり前に受けられる教育」が、いかに多くの歴史的な幸運や、地政学的な奇跡の上に成り立っている、脆いものであるかを痛感させられました。
私たちが「なりたい自分」を追求できるこの環境は、決して永遠でも、普遍的でもない。
それは、先人たちの無数の選択と、国際社会の力学の中で、偶然与えられた「極めて恵まれたスタートライン」に過ぎないのかもしれません。
まとめ
もし、かつての私と同じように、自分のいる世界が全てだと思い込んでいる人がいるとしたら。
一度でいいから、勇気を出して、海外に飛び出してみてほしいのです。
そして、その国のリゾート地だけでなく、人々の日常が息づく場所で、自分の体で生活を体験してほしいです。
目の前で起きた、言葉にできないほどの体験。
その「なぜ?」を、今回紹介したような歴史や地政学といった様々な「視点」を通して振り返ることで、世界は、そして自分自身は、全く違って見えてきます。
それこそが、旅の醍醐味です。
何を見て、何を感じ、何を得られたのか。 いつかどこかで聞かせてもらえたら、これ以上に嬉しいことはありません。
まずは、次に行きたい国の「歴史」を、Wikipediaで一行読むのも面白いかもしれないですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
【もっと知りたいあなたへ(参考文献)】
今回の記事を書くにあたり、特定の書籍だけでなく、様々な情報源から知見を得ました。
もし、このテーマについて、さらに探求を深めたい方がいれば、以下のような分野の資料を手に取ってみることをお勧めします。
- フィリピンの近現代史に関する書籍:
- 例:『物語 フィリピンの歴史』(中公新書)
– スペイン、アメリカ、そして日本との関係性の中で、フィリピンという国がどう形成されてきたかを、読みやすく知ることができます。
- 例:『物語 フィリピンの歴史』(中公新書)
- 開発経済学の入門書:
- 例:『ストーリーで学ぶ開発経済学 — 途上国の暮らしを考える』(有斐閣アルマ)
– なぜ、国によって経済発展のスピードが違うのか。その構造的な要因を学問として学ぶことができます。
- 例:『ストーリーで学ぶ開発経済学 — 途上国の暮らしを考える』(有斐閣アルマ)
- 世界の教育格差に関するレポート:
- ユニセフ「世界子供白書」
– これらのレポートは、データに基づいて世界の教育問題を知るための、貴重な一次情報になります。
- ユニセフ「世界子供白書」

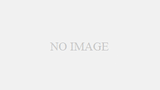
コメント